企業に勤める方にとって、年に数回の賞与支給日は待ち遠しいもの。特に夏の賞与は、6月、7月、8月と企業によって支給日が異なるケースが多いと感じるかもしれません。夏の賞与支給日として、7月10日という日付を耳にすることは多いでしょう。一方で、冬の賞与はほとんどの企業が12月に支給します。この夏と冬の賞与支給日の「ばらつき」の背景には、どのような理由があるのでしょうか。その歴史や業種による違いも交えながら解説します。
夏の賞与支給日が多様な理由
夏の賞与支給日が企業によって異なるのは、主に以下の要因が複雑に絡み合っているためです。
1. 多くの企業の「会計年度末」と「株主総会」のサイクル
日本の多くの企業は、3月末日を決算期としています。決算期が終わると、その会計年度の最終的な業績を確定させ、監査を受け、その後に株主総会を開催して承認を得る必要があります。この株主総会は、決算期から3ヶ月以内、つまり6月中に開催されるのが一般的です。
賞与の支給額は、企業の業績に基づいて決定されることが多いため、最新の決算が確定し、株主総会で承認されて初めて、その後の賞与額を正式に決定できる段階になります。
この一連の流れ(4月:新年度開始、5月:決算確定、6月:株主総会開催・業績最終確定)を経ると、実際に賞与を計算し、従業員に支給する準備が整うのは早くても6月下旬、あるいは7月上旬になるのが自然です。特に7月10日という日付は、このプロセスを踏まえた上で、週明けや月初めの支払日に設定されることが多い典型的な例と言えるでしょう。
2. 労働組合との交渉(春闘)の時期
大企業を中心に、労働組合がある企業では、賞与額を含む賃金改定が「春闘(春季生活闘争)」の中で交渉されます。春闘の決着は例年3月〜4月頃がピークとなり、その決定内容に基づいて夏の賞与額が最終的に固まります。この交渉や決定プロセスに時間を要することも、支給日が6月下旬〜7月以降となる一因です。
3. 企業ごとの締め日や給与計算サイクル
企業の給与計算の締め日や支払日も支給日に影響します。例えば、月末締め翌月10日払いの企業であれば、6月分の給与と合わせて7月10日に賞与を支給する、といった形になることがあります。逆に、月の途中で締める企業であれば、それに合わせて支給日が前後する可能性もあります。
4. 夏の休暇や消費イベントへの配慮
夏の賞与は、お盆休みや夏休みといった長期休暇を前に支給されることで、従業員が休暇をより豊かに過ごせるようにという配慮も含まれています。7月下旬や8月上旬の支給は、お盆休みの旅行や帰省費用に充てやすいという側面もあります。
冬の賞与が12月に集中する理由
一方で、冬の賞与がほとんど12月に集中しているのは、以下のような理由が考えられます。
- 年末年始の消費時期: クリスマス、年末年始、お正月といった一大イベントが控えており、まとまった支出が発生する時期であるため、これに合わせて支給されるのが一般的です。
- 会計上の区切り: 多くの企業にとって、12月は中間決算(9月末締め)や、年間を通した業績予測がより明確になる時期でもあり、賞与額の算定がしやすいという側面もあります。
歴史的背景と業種による違い
歴史的背景
賞与(ボーナス)という制度は、戦後の高度経済成長期に、企業の利益を従業員に分配する形で定着していきました。特に労働組合の組織化が進む中で、春闘を通じて賃金と賞与の交渉が体系化され、「年2回支給」という慣行が確立されました。この際、企業の会計年度や決算、そして春闘の時期との兼ね合いで、夏の賞与は6月〜7月に、冬の賞与は年末の消費に合わせて12月と設定されることが多くなっていったと考えられます。
業種による違い
- 製造業・大手企業: 上述の通り、3月決算〜6月株主総会のサイクルや春闘の影響を強く受けるため、7月上旬〜中旬(特に7月10日)の支給が非常に多い傾向にあります。
- 公務員: 国家公務員や地方公務員の場合、法律や条例で支給日がある程度定められており、夏の賞与は6月下旬(例:6月30日)と比較的早い時期に集中しています。
- サービス業・小売業: 業績が月ごとや四半期ごとに変動しやすいことや、夏休み商戦といった独自の繁忙期を持つことから、6月支給で夏の消費を促したり、逆に8月支給で夏商戦の利益を反映させたりと、柔軟な設定が見られることがあります。また、一部では賞与を月々の給与に上乗せして支給する形を取る企業もあります。
- 外資系企業: 日本の慣習に縛られず、グローバルな給与体系や評価サイクルに基づき、支給時期が日本企業とは異なるケースも珍しくありません。
まとめ
夏の賞与支給日が多様である背景には、企業の決算・株主総会サイクル、労働組合との交渉、給与計算の締め日、そして夏の消費需要への配慮が複雑に絡み合っています。特に多くの企業が3月決算であることから、その後のプロセスを経て7月上旬の支給が定着したと言えるでしょう。一方、冬の賞与は年末年始の消費習慣に強く紐付いており、ほとんどの企業で12月に集中しています。
ご自身の会社の賞与支給日がなぜその時期なのか、こうした背景を知ることで、より理解が深まるのではないでしょうか。


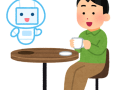

コメント