マイホームの夢を叶える上で、多くの人が直面する大きな選択の一つが「住宅ローンの金利タイプをどうするか」ですよね。大きく分けて変動金利と固定金利がありますが、最近では「変動金利もそろそろ上がるんじゃないか?」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。実際に、日本銀行の金融政策の変更を受け、変動金利にも上昇の兆しが見え始めています。
今回は、そんな最新の金利動向を踏まえながら、変動金利と固定金利の特性、そして変動金利を選ぶ際に知っておきたい「5年ルール」や「125%ルール」について、詳しく解説していきます。
変わり始めた金利の潮目~変動金利に上昇の兆し?~
これまでの日本では、長らく低金利政策が続き、特に住宅ローンの変動金利は歴史的な低水準で推移してきました。そのため、「変動金利を選んでおけば間違いない」という風潮すらあったかもしれません。
しかし、2024年に入り、日本銀行がマイナス金利政策を解除し、量的緩和も終了するなど、金融政策の転換期を迎えています。これにより、短期金利に連動しやすい変動金利にも、じわじわと上昇圧力がかかり始めています。すでに一部の金融機関では、変動金利の上昇が見られるケースも出てきており、今後の動向が注目されています。
一方、長期金利に連動しやすい固定金利は、比較的早い段階で上昇傾向を示していました。変動金利と固定金利の金利差が縮小しつつあるのが、現在の大きな特徴と言えるでしょう。
変動金利のメリット・デメリットと「5年ルール」「125%ルール」
金利が上昇しつつあるとはいえ、変動金利には依然として魅力があります。
変動金利のメリット
- 低金利で借りられる可能性: 金利が低い状況が続けば、固定金利よりも総返済額を抑えられる可能性があります。
- 金利低下の恩恵: 今後、何らかの理由で再び金利が低下すれば、その恩恵を直接受けられます。
変動金利のデメリット
- 金利上昇リスク: 最大のデメリットは、金利が上昇した場合、返済額が増えるリスクがあることです。
- 返済額増加の不確実性: 将来の返済額が予測しにくく、家計の計画を立てづらくなる可能性があります。
ここで、変動金利を選ぶ上で非常に重要なのが「5年ルール」と「125%ルール」です。これらは多くの金融機関の変動金利型住宅ローンに適用されており、急激な返済額の増加を抑えるための仕組みです。
- 5年ルール: 金利が変動しても、毎月の返済額は5年間は変わらないというルールです。金利の見直しは通常半年に一度行われますが、返済額自体は5年間固定されます。これにより、急な金利変動があってもすぐに返済額が増えることはありません。
- 125%ルール: 5年ごとの返済額見直しの際、仮に金利が大幅に上昇していたとしても、これまでの毎月返済額の1.25倍(125%)までしか増えないというルールです。つまり、月10万円の返済額が金利上昇で月15万円になる、といった急激な増額は防がれます。
「5年ルール」「125%ルール」適用後の返済はどうなる?~元本が減らないリスク~
「毎月の返済額が急に上がらないなら安心だ」と思いがちですが、ここが重要な落とし穴です。金利が上昇し、この「5年ルール」や「125%ルール」が適用される状況になった場合、毎月の返済額が変わらなくても、内訳である利息の割合が大きくなり、元金がなかなか減らない、あるいは全く減らなくなる「未払利息」が発生するリスクがあります。
例えば、毎月10万円の返済額で、そのうち利息が2万円、元金が8万円だったとします。もし金利が大きく上昇し、毎月の返済額を125%ルールの上限である12.5万円に抑えられたとしても、新しい金利で計算された利息が12.5万円を超えるような状況になったらどうなるでしょうか?
返済額は12.5万円のままですが、そのすべてが利息の支払いに充てられ、元金が全く減らない、という事態が発生し得ます。これを「未払利息」と呼びます。未払利息は、返済されなかった利息が元金に上乗せされていくような形で蓄積されていきます。
その結果、以下のいずれかの対応が必要になります。
- 最終返済時に一括で未払利息を支払う: ローン完済時に、それまでに発生した未払利息の残高を一括で支払うことになります。
- 返済期間が延長される: 未払利息を消化するために、当初のローン返済期間よりもさらに期間が延長される可能性があります。
- 毎月の返済額が大幅に増える: 次の5年後の返済額見直し時に、それまでの未払利息分を一気に解消するため、返済額が大幅に引き上げられることも考えられます。
このように、5年ルールや125%ルールは、短期的な返済額の急増を抑えるメリットがある一方で、見えないところで利息が膨らみ、元金が減らない(あるいは増える)というリスクを内包していることを十分に理解しておく必要があります。
固定金利のメリット・デメリット
金利上昇局面においては、固定金利の魅力も再評価されています。
固定金利のメリット
- 返済額の安定: 借入期間中の金利と毎月の返済額が変わらないため、家計の計画が非常に立てやすいです。
- 金利上昇リスクの回避: 将来金利がどれだけ上昇しても、ご自身の返済額には影響しません。
固定金利のデメリット
- 変動金利より金利が高い傾向: 一般的に、変動金利よりも金利が高めに設定されています。
- 金利低下の恩恵を受けられない: もし金利が低下しても、ご自身の金利は変わらないため、その恩恵は受けられません(借り換えは可能ですが、手数料がかかります)。
変動金利と固定金利、どう選ぶ?
では、この変動金利と固定金利、どちらを選ぶのが賢い選択なのでしょうか。正解は一つではありません。ご自身のライフスタイルやリスク許容度によって、最適な選択は異なります。
- 金利上昇リスクを避けたい、返済額の安定を最優先したい人:
多少金利が高くても、将来の返済額が変わらない固定金利がおすすめです。特に、収入が不安定な方や、教育費などで支出が増える予定のある家庭には安心感があります。 - 金利上昇リスクを許容できる、低金利のメリットを最大限に活かしたい人:
現在の金利が低い変動金利を選ぶ選択肢もあります。ただし、金利が上昇した場合の返済額増加に耐えられるだけの家計の余裕があるか、定期的に金利をチェックし、必要に応じて借り換えや繰り上げ返済を検討するなどの対応ができるかが重要です。特に「5年ルール」や「125%ルール」のリスク、すなわち元本が減らない可能性を十分に理解し、万一の金利急上昇に備えて、資金を準備しておくなどの対策も検討しましょう。
まとめ:金利動向を注視し、賢い選択を
住宅ローン金利の選択は、何十年にもわたる返済に影響を与える重要な決断です。昨今の金利上昇の兆しは、これまで変動金利一択だった考え方を見直す良い機会と言えるでしょう。
ご自身のライフプラン、家計の状況、そして金利上昇に対するリスク許容度をしっかりと把握することが何よりも大切です。迷った際は、複数の金融機関の金利を比較検討するだけでなく、ファイナンシャルプランナーや住宅ローンの専門家に相談するのも一つの手です。彼らは、個別の状況に合わせたシミュレーションやアドバイスを提供してくれるでしょう。
住宅ローンは、人生で最も大きな借入となることがほとんどです。目先の金利だけでなく、長期的な視点を持って、ご自身にとって最適な金利タイプを選び、安心してマイホーム生活を送ってくださいね。

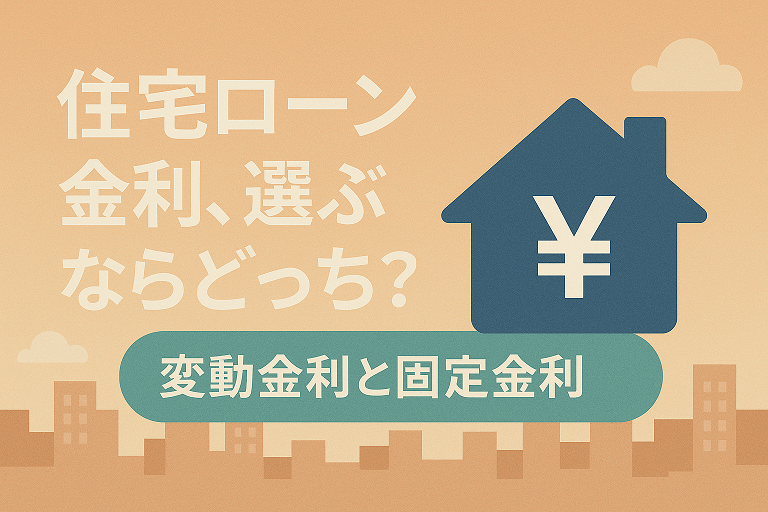


コメント