毎年行われる税制改正。その多くは私たちの暮らしや企業の業務に深く関わってきます。令和7年度税制改正でも様々な見直しが行われましたが、特に給与所得者にとって新たな関心事となるのが、「特定親族特別控除」の創設です。
「一体なんのこと?」と思われるかもしれませんが、これは年末調整の実務に、新たな考慮事項をもたらす可能性があります。冷静に、その内容と現場での影響について見ていきましょう。
「特定親族特別控除」とは何か?
この「特定親族特別控除」は、令和7年分以後の所得税から適用される新しい所得控除です。対象となるのは、控除対象扶養親族(その年の12月31日現在で16歳以上)のうち、特に19歳から22歳の「特定扶養親族」に該当する者です。
従来の、特定扶養親族を対象とする扶養控除では、対象となる親族の合計所得金額が48万円以下であれば、一律で63万円の控除(特定扶養親族控除)が受けられました。しかし、令和7年度の税制改正により給与所得控除等の見直しが行われた結果、この新しい特定親族特別控除では、その特定扶族の合計所得金額が58万円(給与収入で123万円)を超え、123万円(給与収入で188万円)以下の場合に、その所得金額に応じて控除額が変動する、より細分化された仕組みとなります。
年末調整の現場で生じる「問い」と課題
この新たな控除の導入は、年末調整の現場、特に納税者である親御さんと、給与計算を担当する企業にとって、いくつかの新たな課題をもたらす可能性があります。
- 扶養親族の所得把握の難しさ:
- この控除の最大のポイントは、扶養している大学生世代などの子どもの所得金額に応じて、控除額が変わるという点です。特に、下宿などで親元を離れて暮らしているお子様の場合、親がその子どもの年間所得(アルバイト収入など)を正確に、かつ年末調整の時期(通常10月~11月)に見込み額として把握することは、容易ではありません。
- 年末までにアルバイトのシフトが増えたり減ったりするなど、所得が変動する可能性も考慮に入れる必要があります。
- 従業員と企業のコミュニケーション:
- 会社員である親御さんは、年末調整の書類にこの新たな情報を正確に記載するために、お子様に詳細な所得見込みを確認する手間が生じます。お子様側も、自分のアルバイト収入などを正確に把握し、親に伝えるという意識が必要になります。
- 企業側も、従業員からの申告に基づき、変動する控除額を正確に適用するための計算や確認作業が発生します。
従来の扶養控除とは異なり、扶養する側の所得だけでなく、扶養される側の所得も細かく把握・確認する必要が出てくるため、年末調整の複雑さが一層増すことが考えられます。
なぜこのような制度が導入されるのか?(冷静な視点)
この制度創設の背景には、様々な意図があると考えられます。
- 大学生などのアルバイト収入が増加し、従来の制度では実情に合わないケースも出てきていることへの対応。
- 扶養親族の所得に応じた、よりきめ細やかな税負担の公平性を図る狙い。
将来的には、マイナンバー制度の活用や、企業・金融機関・学校などからの情報連携がさらに進み、これらの所得情報を自動的に把握・反映できるようなデジタル化が期待されます。
今後の展望と私たちに求められること
「特定親族特別控除」の導入は、年末調整を「会社任せ」にしていた部分が、より「個人が意識して関わる」方向へ進んでいることの一つの兆候とも言えます。
私たち納税者としては、制度の趣旨を理解しつつ、自身の扶養親族、特に大学生世代のお子様の所得状況について、これまで以上に早めに、そして正確に把握する意識を持つことが重要になるでしょう。企業側も、従業員への丁寧な情報提供や、スムーズな申告手続きのためのサポート体制を検討していくことが求められます。
税制は社会の変化に応じて常に進化します。この新たな控除も、その変化の一つとして、私たちの税金に対する意識や向き合い方を問い直す機会となるでしょう。

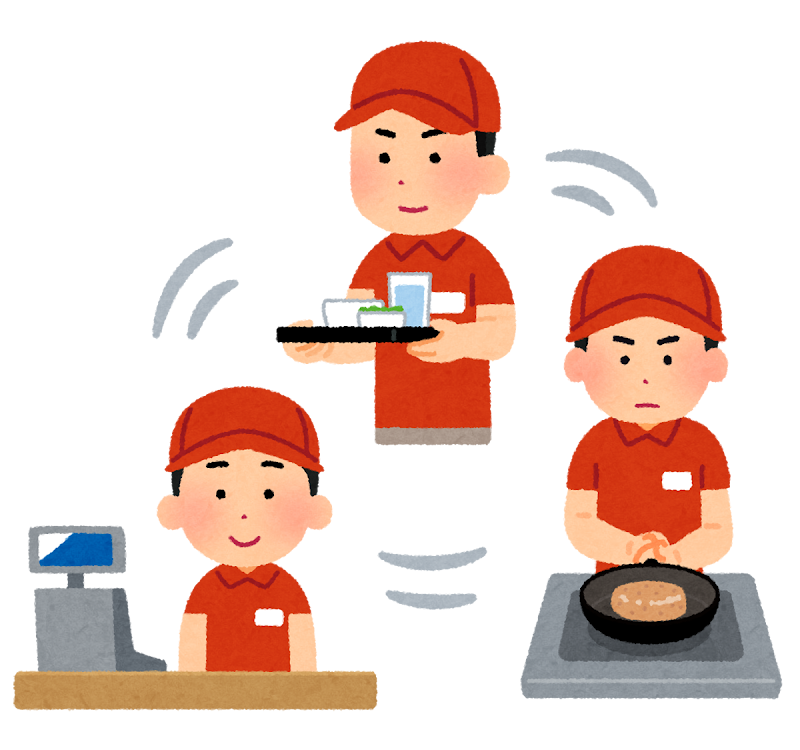


コメント