毎年冬が近づくと、会社員の方々にとって恒例行事となるのが「年末調整」です。保険料控除証明書や住宅ローン控除の書類を集め、会社に提出するこの作業を「面倒だな」と感じている方も少なくないでしょう。しかし、もしこの「年末調整」という仕組みが、ある日突然なくなってしまったら、私たちの暮らしや企業の業務はどう変わるのでしょうか?
そもそも「年末調整」とは?
年末調整とは、企業が従業員の代わりに、その年の所得税の過不足を計算し、調整する仕組みです。会社員の場合、毎月の給料から源泉所得税が天引きされていますが、これはあくまで概算。生命保険料控除や医療費控除、扶養控除など、従業員個々の事情を反映した最終的な所得税額とはズレが生じます。このズレを年末に精算し、払いすぎた税金は還付され、不足分は徴収されるのが年末調整の役割です。
これは、従業員が個々に確定申告をする手間を省き、税務行政の効率化を図るという、日本独自の非常に合理的なシステムとして機能してきました。
「もしなくなったら」企業はどうなる?
もし年末調整がなくなれば、企業の人事・経理部門にとっては、まず間違いなく大きな負担軽減となります。
- 膨大な書類からの解放: 年末に集中する従業員からの控除証明書等の回収、内容確認、そして税務署への提出といった一連の作業が不要になります。
- 計算ミスのリスク減少: 各従業員の税額計算、還付・徴収額の調整といった複雑な計算業務から解放され、ミスのリスクが大幅に減少します。
- リソースの有効活用: 年末調整に費やしていた膨大な時間と人員を、他のより戦略的な業務や、従業員満足度向上に資する業務に振り向けることができるでしょう。
企業にとっては、事務作業の効率化という点で大きなメリットがあるように見えます。
「もしなくなったら」個人はどうなる?
しかし、その分、個人の負担は大きく増大します。
- 全員が「確定申告」の対象に: 年末調整がなくなれば、原則として給与所得者も全員が自分で確定申告(所得税の申告)をしなければならなくなります。
- 控除の自己管理が必須に: 生命保険料控除、医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除など、税金を安くするための各種控除は、すべて自分で書類を管理し、申告書に記入して提出する必要が出てきます。
- 税務知識とデジタルリテラシーの必要性: 確定申告書の作成には、ある程度の税務知識が不可欠です。また、今後申告のデジタル化がさらに進むことを考えれば、e-Taxなどを使いこなすデジタルリテラシーも必須となるでしょう。
- 還付金の受け取りや不足税額の納付も自己責任: 払いすぎた税金を確実に還付してもらうためには、忘れずに、かつ正確に確定申告をしなければなりません。逆に不足額が生じた場合は、自分で納付の手続きを行う必要があります。
多くの会社員にとって、税金は会社任せだった部分が、自己責任へと大きくシフトすることになるでしょう。
「年末調整ゼロ」は実現可能か?~デジタル化の先に描かれる未来~
では、そもそも年末調整をなくすことは現実的なのでしょうか。
現在の日本の税務システムを考えると、年末調整がなくなれば、国税庁への確定申告件数が激増し、対応が困難になることが予想されます。この問題をクリアするには、以下の要素が不可欠となるでしょう。
- 完全な情報デジタル連携: マイナンバー制度をさらに活用し、雇用主からの給与情報、金融機関からの保険料・住宅ローン情報、病院からの医療費情報など、すべての所得・控除関連情報が税務当局に自動で、リアルタイムに連携される仕組みが不可欠です。
- リアルタイム税額計算・調整: 毎月の給与支払い時などに、すでに全ての情報が反映された状態で税額が計算・調整されるシステムが導入されれば、年末の精算は不要になるかもしれません。
- 納税者への徹底した情報提供とサポート: 確定申告の負担が増える分、国税庁からの情報提供や、AIチャットボット、オンライン相談などのサポート体制を飛躍的に充実させる必要があります。
欧米の一部には、年末調整のような仕組みを持たず、給与からの源泉徴収のみで完結したり、個人がすべて確定申告を行う国もあります。しかし、その国の税制は日本のそれとは大きく異なるため、単純な比較はできません。
見直される役割と、私たちの準備
年末調整は、企業と個人の双方にとってメリットがあるからこそ、長年日本の税務システムに存在し続けてきました。しかし、デジタル化の進展は、その役割や必要性を改めて問い直すきっかけを与えてくれます。
すぐに年末調整がなくなることはないかもしれませんが、マイナンバーカードの普及やe-Taxの進化を見ても、税務行政のデジタル化は着実に進んでいます。将来的には、より簡素化された、あるいは自己申告の比重が高まる税制へと移行する可能性も十分に考えられます。
いずれにせよ、私たち一人ひとりが、自分の税金や社会保障についてより高い関心を持ち、デジタルツールを使いこなす能力を身につけていくことが、今後ますます重要になるでしょう。


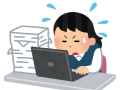

コメント